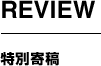
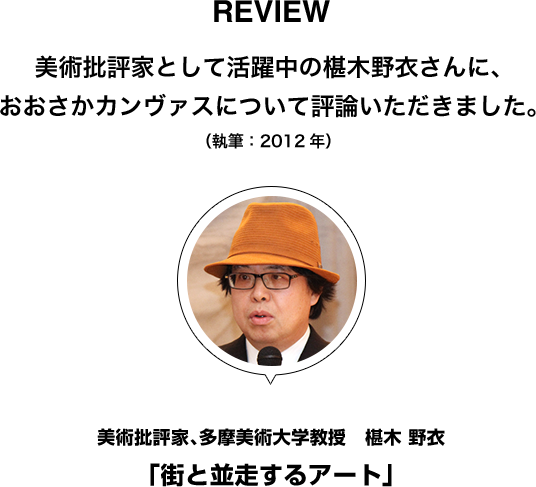
アートの理解をめぐって、近年、日本ではいささかおかしなことが起こっている。
美術、とりわけアートと呼ばれる最新の文化は、いつでも都市や街を舞台に発達してきた。考えてみればそれはあたりまえで、若く無限の可能性を持つ美術家の卵が、最初から立派な美術館や画廊で発表の舞台を与えられるわけではない。けれども、せっせと家や小さなアトリエで心魂を込めて描き貯めた作品を誰かに見てほしい。ありのままの感想を聞きたい。そんなとき、あなたならどうするか。
どこでもよい。いっそのこと街に出て、発表のチャンスを探すのではないか。喫茶店の一角、古本屋の片隅、神社の境内、いや、もしかしたら道や広場のまっただ中に絵を並べても、誰かに見てもらいたいと思うのではなかろうか。
これは仮の話だけではない。実際、日本で最初に油絵を見せた画家、五姓田芳柳が発表の場所に選んだのは、浅草の浅草寺の境内だった。芳柳はそれを茶屋にしたて、訪れた客に茶を振る舞い、絵を語る人たちの交流も促した。いまでもたまに、カフェというよりは昔から変わらぬ風情の喫茶店の壁を借り、画家の個展が催されているのを見掛けるが、これも、実は明治最初の油絵展の名残にほかならない。
こうした流れは、長く文部省(現・文部科学省)が指導してきた美術のあり方とは、まったく違っている。国の文化政策は、むしろ作品を街に開くどころか、美術館に幽閉して来た。それは、「展示」とならぶ美術館の二大機能である「収蔵」という言葉に集約されている。いや、どんな展示も収蔵がなければ成り立たないのだから、収蔵は展示に先立つと言ったほうがいいだろう。この意味では、収蔵こそが美術館の心臓だと言える。収蔵とは「蔵に収める」と書く。展示とは、その「蔵を開いて示す」、いわば宝物の開陳である。それを象徴するのが「国宝」という言葉だ。「宝」となれば、誰でも皆、ありがたがらなくてはならない。
アートは、これとはまったく異なる素性を持っている。アーはもともと、「お宝」という発想を否定するところから始まった。ところが、日本では国宝もアートも同じ文化政策のなかで捉えられている。だから、アートもまた、「お宝」の延長線上に見られてしまう。たぐいまれな文化の所産を「鑑賞」する、という姿勢の奨励だ。けれども、こんな考えは文化の後進国に特有の「症例」と言うべきだ。アートを宝物のように鑑賞しても、得られるものはない。アートは「鑑賞」するのではなく「参加」するものだからだ。この勘違いから、アートは難解だとする広く共有された誤解も生じる。日本でアートの力を本当の意味で浸透させ、おおいに発揮させるためには、まずこの考え(アート=最新の宝=ありがたく鑑賞)をあらためなければならない。
「おおさかカンヴァス」に初めて接したのは、昨年も押し迫った暮れのことだった。一泊二日の短い滞在で、見られた作品も限られていたけれども、画期的な事業だと驚かされた。今後、大阪という街が刺激される原動力となる可能性も感じた。しかしそのことについて立ち入るためには、もう少し、アートの定義そのものにかかわる意味について話しておかなければならない。
私たちがいま知るような意味で美術が「美術」になったのは、そう遠い昔のことではない。西洋近代の市民革命を経て、はじめて美術は「美術」になった。それ以前はどうだったかというと、美術とは王侯貴族のものだった。すでに17世紀には、オランダで新興の商人たちが絵画をインテリアとして家に飾るようになっていたが、これもまた、スペインとの独立戦争を経て、王侯貴族の宮殿型美術とは異なる、自分たちの家に飾れる美術を興そうという考えがあったからだ。フェルメールが日常の何気ない一コマや街の風景を描いたのは、このささやかな抵抗のあかしでもあった。
市民によるこうした美術の奪還が、もっとも大規模に開花したのが、近代の公的な美術館である。ルーブル美術館もエルミタージュ美術館も、みな王侯貴族の華やかな財をしまい込むための、いわば「蔵」であり私有物にほかならない。ゆえに、一般の市民がそれを目の当たりにすることはできなかった。逆に言えば、隠されたものを公にする力を得ること、それが市民革命の成果でもあった。だからこそ、王侯貴族が世界史の檜舞台から去ったあと、これらの宝物庫が「誰のものでもない」公共の財として広く開かれたのは、市民による革命が成功したことの象徴的な意味を持つ。わたしたちがいま知る美術館はこうして、実は流血の犠牲のうえに成り立つ。西洋で美術館がたんに文化の「鑑賞」に留まらぬ意味を持ち、絶えず論議の的になっているのには、こういう背景がある。
だからこそ、今日の美術館は、根本的に市民に開かれたものでなければならない。この点、日本の美術館はおうおうにして「公」という言葉の意味をはき違えている。近代化が事実上の無血革命と制度の輸入によって成し遂げられたため、そのあたりがあいまいになっているのだろう。が、近代の公とは定義上、市民による市民のための「解放」を前提にしている。だから、文化は決して「宝」であってはならない。宝という考えそのものに、根本的に前時代的な意識がこびりついている。宝を収める「蔵」の所有者が王侯貴族から国家に変わったのでは意味がないのだ。だからこそ、美術館は(作品の保存という使命を超えて)秘匿的であってはならないし、ましてや、文化を司ろうとする官僚族の価値判断の反映などであってはならない。私的な価値観によって築かれた「蔵」を壊し、「宝」を広く多様な公に開放することから、今日の美術館は始まったからだ。
おおさかカンヴァスを見て気づいたのは、そこで目指されているアートの公共性が、いま書いてきたような「美術は市民のもの」という考えを、かなり徹底した次元で示そうとしていることだ。美術館を出て「街や野外を舞台にアートを」という動き自体は、昨今とくにめずらしいものではない。けれども、そうした試みは、あらかじめ美術館を逸脱しうる範囲を行政が規定し、その枠の中で収めようとする「囲い込み」のアートであることが大半だ。要するに、旧来の「蔵」としての美術館の考えを街に置き換え、公共の場所を制限付きで展示施設化しているにすぎない。これは一見、アートを街に開くようでいて、実際は、行政による公共の場所の管理体制の強化にすぎない。
ところが、おおさかカンヴァスでは、「公共空間の開放を目指し、行政自身が規制緩和も辞さずに作品の展示・発表を支援」することを事業の主旨としている。つまり、行政による規制の枠内で、アートを公共という名のもとの「蔵」に収めようとするのではなく、美術館がもともと持っていたはずの市民による「脱蔵化」の考えに乗っ取って、場合によっては規制を緩和しても、街を本来の意味で美術館化(人々に開放)するということだ。
また、おおさかカンヴァスでは、国の緊急雇用創出基金を利用し、失業者を政策補助や作品案内人として雇用。またニートやひきこもりの若者を支援している事業者とも組み、そういった方々をアートの制作現場に派遣、社会復帰へのステップの支援も視野に入れて取り組んでいる、としている。街や屋外を含めて展開されるビエンナーレ、トリエンナーレ形式の美術展もまた、近年、日本で盛んに開かれるようになった美術展の形式だが、アーティストのアシストを、過度にボランティアに負いすぎているケースをしばしば見掛ける。むろん、積極的な意思にもとづくボランティアは歓迎すべきことだが、そうした活動が成り立つのは、参加者自体がアーティストを目指す美大生であることが多く、そのための経験を積む「修業」的機会として捉えられているからだ。そこから学ぶものは少なくなかろうが、こうした特定のジャンルの教育機会として活用されるだけでは、本来の意味でのアートの開放と言うことはできない。「美術」という制度の外と繋がることで、はじめてアートは街に開かれるのである。おおさかカンヴァスが、失業者やニート層の若者に対し、アートを媒介に一定の雇用関係を前提に参加機会を提供し、そのことでかれらが街と具体的に繋がることが実現できれば、日本の美術展として画期的なことだ。
もともと、街や郊外へとアーティストたちが進出するようになった1960年代後半、用意された美術館で悠々と個展をする美術家に比べ、かれらははるかにマイナーな存在であった。また、かれらが自力で見出した発表の場所は、殺風景な河川の護岸に立てられた倉庫であったり、野原に打ち捨てられた空き家だったりした。そうした場所は治安も悪く、治安が悪い代わりに経費も掛からなかった。けれども、アーティストがそうした場所に果敢に取り組み、いつしか風景が魅力あるものに変わることで、しだいに人が訪れるようになり、いつのまにか見違えるような場所に変わる事例が増えるに連れ、かれらの活動に広く注目が集まるようになってゆく。とりわけ欧米では、行政がその効果に注目し、アーティストの活動を積極的に支援することで、かれらの力を借り(引き出し)、街を再開発するプロジェクトが増えていった。が、これは、日本で依然として多い、いわゆる「村おこし」的なアート・プロジェクト(いまある街はそのままで、粉飾的にアートを利用する)とは、一線を画する考えを必要とする。アートの力を借りることは、街が積極的にみずからを変えようとする姿勢なくしてはありえない。そのためには、受け入れる側にも、アートに潜在する未知の可能性に見合うだけの覚悟が必要なのだ。
おおさかカンヴァスを見ていると、日本でもいよいよ、本当の意味でアートが裸の街へと投げかけられつつあるのを感じる。今後のますますの展開を、目を見開いて追い続けたい。