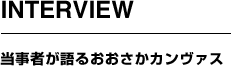
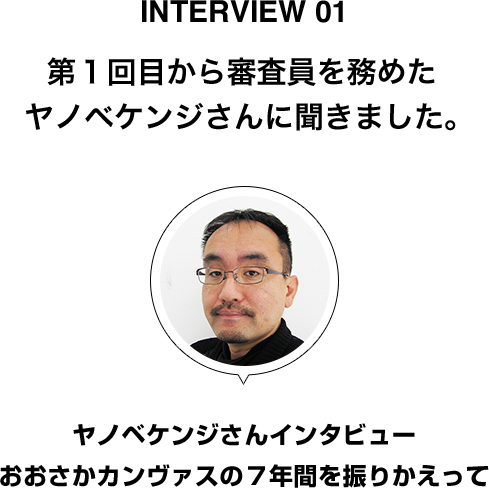
ヤノベさんは第1回のおおさかカンヴァスから審査員を務めてくださいました。審査ではいつもアーティストの視点から、個々の作品の実現可能性や展示の全体像などについて鋭い意見をいただき、単なる審査員の役割のみならず、カンヴァス全体のディレクター的役割も果たしてくださいました。
ヤノベさんにカンヴァスの意味などについてお話をお聞きしました。
「おおさかカンヴァス」の第一回目が何の因果なのか大きな震災に重なりました。レセプションの日の前日に東日本大震災が起こり、レセプションもキャンセルになって、アーティストも混乱していました。
象徴的なのは美術作家の加藤翼さんが、大勢の人の力を合わせて巨大な構造物を引き倒すという作品のパフォーマンスについて悩んでいたことです。被災地の状況を伝えるメディアから繰り返し流され続ける、破壊された建物などの映像と、巨大な箱を引き倒して壊すという自分の作品行為のビジュアルがあまりにも似ているため、パフォーマンスを実施していいのか結論を出せずにいたのです(震災の起こった翌日がパフォーマンス実施日にあたっていた)。最終的には、構造物を引き倒すのではなく、力を合わせて“引き起こす”作品というアイデアに転化していきました。加藤さんはその後もずっと、引き起こす作品をつくり続けることになります。

現実の壮絶な出来事によって、自分の表現行為も変化せざるをえないという状況が「おおさかカンヴァス」第一回目に起きて、そこである意味<アートとはいったい何なのか?>という問いを突きつけられたわけです。美術のための美術をつくっていた人たちにとってみると、自分たちの価値観の底が抜けてしまったような、いったい何のために自分はものをつくって表現しているんだろうという問いを、改めて考えざるをえないことが起こったと思っています。芸術がただの自己表現で終わるものではなく、世の中にどんなかたちで存在しうるものなのか、大きい視点から考えざるをえない環境が「おおさかカンヴァス」が始まった起点の中に潜んでいたのではないかと思うのです。
街中に作品を置くということは、美術の文脈や歴史の中で作品が読み解かれるのではなく、そういうことを知らない人でも享受することができるわけですから、それを自分たちの文化として読み込み、そして自分たちの生活の中で作品がどう作用するのかということを、考え、つなげていかなくてはいけない存在であるということを、改めてアーティストは問われたのではないかと思っています。
「おおさかカンヴァス」の記録を振り返っても、そういうものに応えうるような作家や作品が選ばれている印象があり、そういう作品が場所のポテンシャルを開示し、都市の可能性を開いてきたのだと思います。アートという先行者によってまちが開かれたからこそ、例えば、何もなかった埋立地で「おおさかカンヴァス」が開催された翌年に「劇団 維新派」の公演が実現し、さらにその翌年には常設の商業施設である中之島漁港がオープンするなど、アートによる都市の再生につながる事例が生まれたのだと思います。


「おおさかカンヴァス」は作品が狭い世界に閉じこもるのではなく、まちの可能性を開く役割をアートが担うという、ある種のアートの使命を明確にするコンペになっていったと強く思っています。震災がきっかけとなって、ものごとの大きな価値観がひっくり返り、改めて目の前の現実から何をすべきかを問い直されている状況に対して敏感に反応しているコンペティションになったという意味では、「おおさかカンヴァス」はほかの制度化された展覧会や芸術祭とは一線を画す、都市の潜在能力に対して「どう戦えるのか」という命題を与えられた芸術家たちの記録になったのでは、と思います。
それは僕の視点だと思いますが、震災によって、美術の狭い世界の中だけで作品をつくっている者からすれば、自分の作る作品が“美術のための美術”ではなくて、パブリックが必要とする存在であるべきではないのか、ということを改めて考えさせられたと思うのです。
つまり、作品が人の心を動かしたり、あるいは都市の機能に変化をもたらしたり、<多くの人や社会に向けて、可能性の扉を開くような存在でなくてはならない>ということを問われているのではないか、ということです。「おおさかカンヴァス」をふり返って思うのは、社会の扉を開くというのは、とてつもないエネルギーやインパクトが必要で、それを小難しい美術の文脈で御託を並べるよりも、もっとストレートで誰にでも届くような表現を選択することが非常に有効であり、今までの美術家のプライドを投げ捨てて挑んでいける作品のほうが結果的に強いということを思い知らされました。
「おおさかカンヴァス」は、強いアイデアを具体化できる仕組みを持ったコンペです。つまり美術表現の専門家でない人がフレッシュなアイデアを、アートマネージャーや行政のサポートを受けて、きちんとした具体的な作品として実現することができます。さらに、それが多くの人に評価されて、まちの可能性を開いていくような結果をも生み出しているということにおいて、今までにないアートの価値観を発見、発掘し、同時に新しい概念を発明したプロジェクトになったと思います。
美術というカテゴリーの狭い領域の中で、内向きに発信されていたものの限界を突きつけられ、僕自身も歪んだ状況の中で限界を感じているし、それを今の時代が受け止めることができない現状も感じていますが、「おおさかカンヴァス」はそれにいち早く敏感に反応してきました。一見、一発ギャグ的にとらえられたり、美術ではないというふうに思われたりするけれど、「じゃあ美術とは何なんだ」と、逆に鋭く突きつけている文化事業なのだと思います。